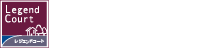「一生に一度の買い物」と言われる高額なマイホーム。もしも親からの資金援助があれば、購入への力強い後押しになります。
「一生に一度の買い物」と言われる高額なマイホーム。もしも親からの資金援助があれば、購入への力強い後押しになります。
基本的に、親からもらったお金でも法律上は「贈与」なので、年間110万円を超えると贈与税がかかります。ただし住宅取得用の資金の贈与を受けた場合は一定額まで非課税となり、これに相続時精算課税制度を併用することで、最大3,610万円まで贈与税が非課税になる可能性があります。
贈与税の負担を軽減しつつマイホームの自己資金を増やせるチャンスですから、親からの資金援助が期待できる場合は、これらの非課税制度に注目してみましょう。
マイホーム資金の贈与にかかわる非課税制度
親から住宅取得用の資金の贈与を受けた場合に、要件を満たすと贈与の一定額が非課税になる制度は次のとおり。
①贈与税の基礎控除(暦年課税)
②住宅取得等資金の非課税制度
③住宅取得等資金の相続時精算課税制度の特例
以下、詳しく見ていきましょう。
①贈与税の基礎控除(暦年課税)
贈与には1年間に110万円の基礎控除額があります。1月1日から12月31日までの間に贈与を受けた金額が110万円を超えなければ、贈与税はかからず、申告の必要もありません。
なお、贈与税の課税方式には「暦年課税」と「相続時精算課税」の2つの方式があり、この110万円の基礎控除を使えるのは暦年課税方式の場合となります。
②住宅取得等資金の非課税制度
2026年12月31日までに親や祖父母から住宅取得のための贈与を受けた場合、要件を満たしていれば、省エネ等住宅(※)なら1,000万円まで、省エネ等住宅以外の一般住宅なら500万円までが非課税になります。
※省エネ等住宅とは…
省エネ性能・耐震性能・バリアフリー性能のいずれかの基準(省エネ等基準)に適合している住宅のこと。
この住宅取得等資金の非課税制度は、①の贈与税の基礎控除(暦年課税)、または③の相続時精算課税の特例との併用も可能です。
③住宅取得等資金の相続時精算課税の特例
相続時精算課税とは、60歳以上の親や祖父母から18歳以上の子どもや孫への贈与について、110万円の基礎控除に加え、特別控除として2,500万円まで非課税になる制度。住宅取得用資金の贈与の場合、2026年12月31日までは特例として、親や祖父母が60歳未満でも制度を利用できます。
相続時精算課税では2,500万円までの贈与は非課税ですが、相続時に、贈与を受けた金額と相続財産の合計額が相続税の対象となります。
また、②の住宅取得等資金の非課税制度との併用も可能で、併用した場合は最大3,610万円まで非課税で贈与を受けることができます。
非課税になる上限額をまとめると…
①贈与税の基礎控除(暦年課税)のみ
…年間110万円まで非課税
②住宅取得等資金の非課税制度 + ①贈与税の基礎控除(暦年課税)
・省エネ等住宅の場合…1,110万円まで非課税
(住宅取得等資金の非課税枠1,000万円、基礎控除110万円)
・一般住宅の場合…610万円まで非課税
(住宅取得等資金の非課税枠500万円、基礎控除110万円)
②住宅取得等資金の非課税制度 + ③住宅取得等資金の相続時精算課税の特例
・省エネ等住宅の場合…3,610万円まで非課税
(住宅取得等資金の非課税枠1,000万円、相続時精算課税の特別控除2,500万円・基礎控除110万)
・一般住宅の場合…3,110万円まで非課税
(住宅取得等資金の非課税枠500万円、相続時精算課税の特別控除2,500万円・基礎控除110万)
適用のための要件などをチェック
贈与の一定額が非課税になる各制度の詳しい要件などは、国税庁のサイトやパンフレットで確認できます。
・国税庁「住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税」等のあらまし
住宅取得のための贈与のお得な非課税制度は、もしも資金援助を受けられるなら有効活用したいところ。適用のための要件などを確認して、早めに準備を進めておきましょう。